こんにちは!ココモの唐土(モロコシ)です。
今回はご夫婦揃っての「老後に必要なお金」、「おひとりさまの老後の場合」、「貯金/貯蓄」の他、「早くから独身になった場合」まで含めた「必要なお金の考え方(計算方法)」について紹介します。
「数字」を捉える「イメージ」について
老後〇〇万円必要だとよく聞きますが、その「数字」は、「平均身長」や「平均体重」のようなものです。身長150cmは低めです。180cmは高めです。しかし、だからといってそのことで毎日の生活にそれほど差はありません。同様(?)に、日本人の平均年収が〇〇万円だとしてもそれより多いからといって幸せとは限らず、少ないからといって不幸とは限りません。
つまり、「老後月々〇〇万円が必要ですよ」とか、「趣味を楽む定年後は〇千万円必要ですよ」という数字は全ての人には当てはまらないということです。各自の価値観や次のような条件で随分変わります。
- 家や家賃の有無
- 年金や保険に入っているか否か
- 車を所有するか否か
- 老後の収入源の有無
- 高額な趣味の有無
- 扶養してくれる家族の有無
- 住むところは都市か田舎かはたまた海外移住するか ・・・・・・・・・
次に紹介される「金額の資産」を用意できなければ難民老人になるとは限りませんので「妙な不安感」にさいなまれないようになさってください。平均的な数値を使った「計算の考え方」に過ぎないです。
具体的に計算してみましょう
あなたの年齢がこれには当てはまらないかもしれません。しかし、まずは分かりやすい数字で計算してみることでおおよその全体像が把握できます。その後に、実際にあなたの数字を当てはめて計算してみてください。
こういうケースを考えてみましょう
- 夫 45歳、妻 40歳、長男 10歳、長女 5歳
- 夫 一家働き手、妻 専業主婦
- 現在の生活費 40万円
- 末っ子の就職して独り立ち 20歳
- 生活費の現在からの変化
- 夫が死亡した場合 7割(子供が居る)
- i後、更に末っ子が就職後 5割
- 夫が60歳で定年退職後 7割
- iii後、更に夫が先立った場合 5割
- 平均余命は下記とする(ある年の厚生労働省発表より)
まずは生命表の見方から
小難しく見える生命表ですが、これが数字を考える根本です。掛け算ができるようになるには九九ができなければならないようなものです。老後の費用を考えるまでに、まずはこの表をじっくりご覧になってください。
- (一番左の上)50歳の男性 あと32年生きる
- (その右隣)50歳の女性 あと38年生きる
- (一番左の下)59歳の男性 あと23年生きる
- (その右隣)59歳の女性 あと29年生きる
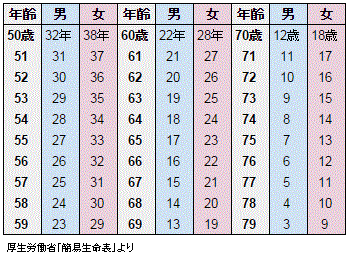
ご夫婦揃って平均的に生きる場合の生活費の例
では、いよいよ上の生活を営む年数に基づいて老後に必要な費用を計算してみましょう。実際電卓をたたいてみると結構シンプルです。何度かやって慣れれば即座に計算できるようになります。
- 定年までは夫の収入があるとして考えません
- 子供はどちらも二十歳で独立したとします
- 夫が定年退職した後の「夫婦揃っての生活資金」
- 夫の退職(60歳)からの余命(生命表から) 22年
- 22年×12ヶ月×40万円×7割(iii)=7,392万円
- 夫の平均寿命(82歳)後の妻の一人の老後資金
- 夫の平均寿命時、妻(77歳)からの余命 11年
- 11年×12ヶ月×40万円×5割(iv)=2,640万円
- ご夫婦平均余命までの合計
- 上記(3+4)=10,032万円
夫が先立ってしまった場合の生活費の例
- 夫が死亡した場合の「家族の生活費」
- 末っ子が社会に出るまで 5歳→20歳=15年
- 15年×12ヶ月×40万円×7割(i)=5,040万円
- 1.の末っ子が独立後の「妻の生活費」
- 独立時の妻の年 35+15=50歳→余命(生命表から)38年
- 38年×12ヶ月×40万円×5割(ii)=9,120万円
- 夫が先立ってしまった場合の合計
- 上記(1+2)=5,040万円+9,120万円=14,160万円
実際はどうか
これは数字を簡単にし、表示以外の要素を全て除いた簡単な計算例です。実際は・・・
- 給与やボーナス等収入が増える(減る)や退職金
- 物価が上がる(下がる)
- 年金に入っている(老後支給される)
- 寿命がもっと長かったり、もっと短かったり
- 怪我や病気での出費
- 個人で入った保険や年金
- 家のローン、親の財産や負債の相続
- その他、宝くじに当たる、競馬で万馬券、地震・雷・火事・噴火…etc
準備もしているはず
日本における生命保険の加入率はとても高い加入率です。以前は保険に入る理由は「(よく分からないから)勧められたから」というのが多く、現在は「希望に合った保険だったので」と変わってきています(生命保険文化センター調査)。
ところがこれらの数字を踏まえた過不足の無い運用をされておられる家庭はどれくらいあるでしょうか。他のページはもっと異なる視点からご自身のライフプランニングが立てやすい情報を増やしていきます。小難しいところはさておき、興味をもたれたところを参考に、旅行に行くならよりよいプランを検討するように、よりよいライフプランニングを行ってみてください。
